はじめまして
今まで転勤のために、県外各地で茶道を経験して参りました。
平成16年より、終の住処に茶室を設けて四季折々の道具を
取り合わせ、お菓子も自家製手作りにして茶の湯を楽しんでおります
茶室は四畳半・四畳半台目・八畳広間・大炉といろいろ稽古できます。
又、折々に茶事・花月も楽しめる茶の湯の道場です。
|
| 稽古場紹介 |
|
 |
露地の枝折戸
枝折戸を開けて見える露地です。
|
蹲(つくばい)
|
 |
 |
腰掛待合 |
| にじり口 |
 |
 |
|
茶室四畳半部屋から見たにじり口
連子窓と壁には腰張りがしてあります。 |
 |
 |
四畳半台目席
棹緑天井、化粧屋根裏掛け込天井、
網代落天井からなる三段構成の
四畳半台目茶室は二重の仕付棚を
配した台目出炉席です。
又、畳を敷き替え風炉先屏風で
仕切れば、四畳半本勝手席にも
代わります。 |
| |
 |
 |
八畳広間の席
八畳の茶室は、広間炉本勝手
大炉、釣釜にも使用出来ます |
|
|
| |
|
お稽古も毎月変わります。
※写真のお菓子は全て先生手作りです。 |
| 11月 |
 |
開 炉 |
冬かぶら
練り切り 先生手作り |
 |
 |
炉開きに出される
粟善哉(あわぜんざい)
先生手作り |
| |
|
| 12月 |
|
菓子 薯蕷きんとん 先生手作り
銘 ・・・ 聖夜
|
 |
| |
|
| 1月 |
|
 |
初釜 |
柚子饅頭(薯蕷)
先生手作り |
 |
 |
福寿草 練切り
先生手作り |
| |
|
| 2月 |
|
 |
大炉 ・・・ 逆勝手点前 |
| 極寒の”2月”だけの大炉 |
 |
 |
銘 下萌え
練り切 先生手作り |
| |
|
| 3 月 |
|
 |
釣 釜 |
| |
 |
 |
銘・・・桃の里
練り切り 先生手作り |
落雁 銘・・・菜の花
先生手作り |
 |
| |
|
| 4 月 |
|
 |
銘 佐保姫 (春をつかさどる女神)
煉切 先生手作り
|
| 透木 裏ごう釜 |
 |
 |
花見団子 先生手作り
紅(花)、緑(草)、茶(土)をイメージ
お団子も食べ方があります |
銘 花紅
薯蕷(じょうよ)きんとん
先生手作り |
 |
| |
|
| 五月 |
初風炉 |
 |
|
| 灰型 二文字押切 |
 |
 |
銘 卯の花
薯蕷練切り(先生手作り) |
銘 青梅
練切り(先生手作り) |
 |
| |
|
 |
桑小卓で・・・ |
| |
|
| 6月 |
|
菓 子
銘 水無月
外郎製 先生手作り |
 |
| |
|
| 7月 |
|
 |
遠山の灰型 |
| 台目席の点前座 |
 |
 |
葉蓋のお点前 |
| |
|
| 8月 |
|
|
 |
 |
名水点 |
| |
|
| 9月 |
|
|
 |
 |
銘 着せ綿
練り切り 先生手作り |
| |
|
| 10月 |
|
向山の灰型
|
 |
 |
銘 山苞(やまずと)
先生手作り
|
五行棚
中置の点前座 |
 |
 |
大板
中置の点前座 |
らくがん・・・紅葉
雲平・・・いちょう
先生手作り |
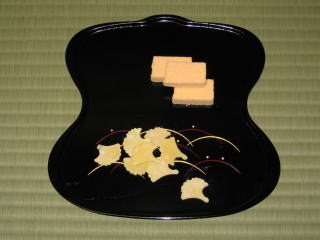 |
 |
水屋
基本に沿った使いやすい水屋に
しています。 |
| |
このページの先頭へ |